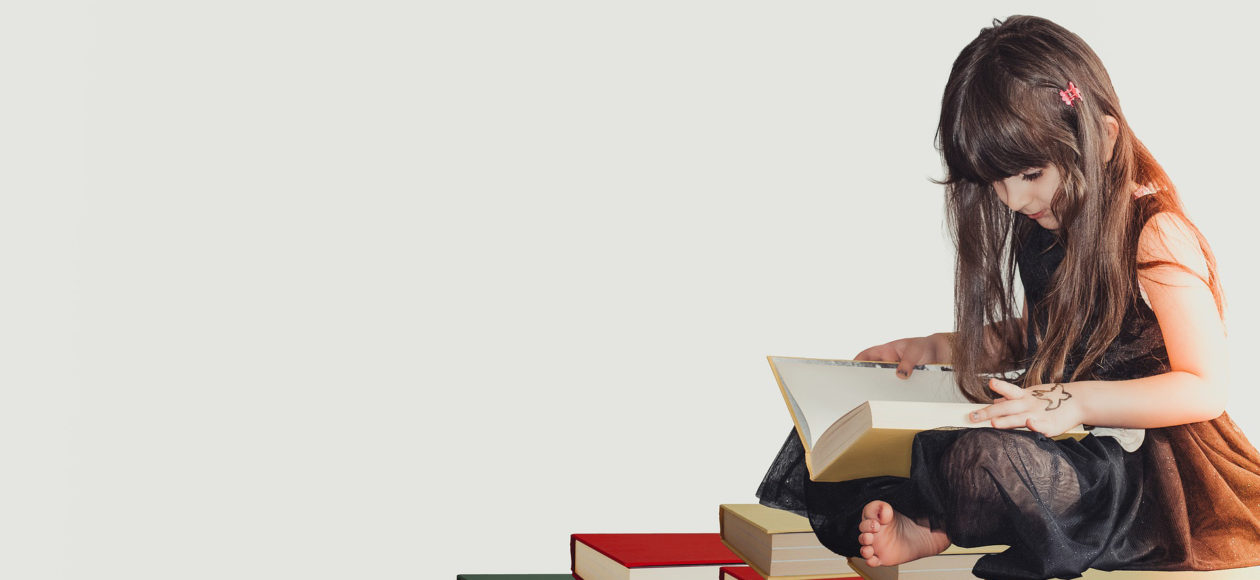「空気」に抗い「水」を差す自由
「「空気」の研究」(山本七平)文春文庫

十数年くらい前に「KY」、
つまり「空気読めない」なる語が
流行ったことがありました。
学校でも、子どもたちは
空気を読むことが
大切なのだと勘違いしていました。
そのとき思ったものです。
「空気なんか、読むな!」と。
でも、子どもたちに言っても
難しいのです。
なぜなら大人でさえ、
その場の空気を
読んでしまうのですから。
その「空気」について、
考察した評論が本書です。
戦艦大和の無謀な出陣を例に引き、
「あらゆる議論は最後には
『空気』できめられる。
最終決定を下し、
『そうせざるを得なくしている』力を
もっているのは一に『空気』であって、
それ以外にない。」
と山本は説きます。
そして次のように
「空気」を分析しています。
「『空気』とはまことに
大きな絶対権をもった妖怪である。」
「日本には『抗空気罪』という罪があり、
これに反すると
最も軽くて『村八分』刑に処せられる」
本当に「空気」とはやっかいな代物です。
さらに山本は、
「水」についても考察を重ねています。
ここで言う「水」とは、
「水を差す」の「水」です。
「何か強力な
消化酵素のようなものがあり、
それに会うと、すべての対象は
まず何となく輪郭がぼやけ、
ついで形がくずれ、
やがて溶解されて影も形もなくなり、
どこかに吸収され、
名のみ残って実体は消えてしまう」
と述べています。
つまり、大きな絶対権を持ち
抗うことのできない「空気」を、
雲散霧消させてしまうのが
「水を差す」ことなのだそうです。
その上で著者は、
社会における「自由」とは、
この「水を差す自由」の
ことであると説きます。
空気に束縛されず、一人一人が
自分の考えを述べることができる。
そうした環境をつくりあげるのは、
日本ではまだまだ
難しいのかもしれません。
いじめの問題が
大きく取り上げられています。
幸いにも私の住む地域では
目立ったいじめは報告されていません。
私自身、教育現場にいて、
この20年の間に子どもたちは
素直で立派になったと感心しています。
それはある意味、
「いじめはいけない」という空気が
教室に存在しているからだと感じます。
それ自体はいいことなのですが、
様々な「同調圧力」としての「空気」が
同時に存在しているのもまた確かです。
それに適応できない子どもは
息苦しいと感じることもあるでしょう。
「水を差す自由」を保証し、
「水を差す力」を身に付けさせることも
必要なのだと感じています。
(2019.7.18)