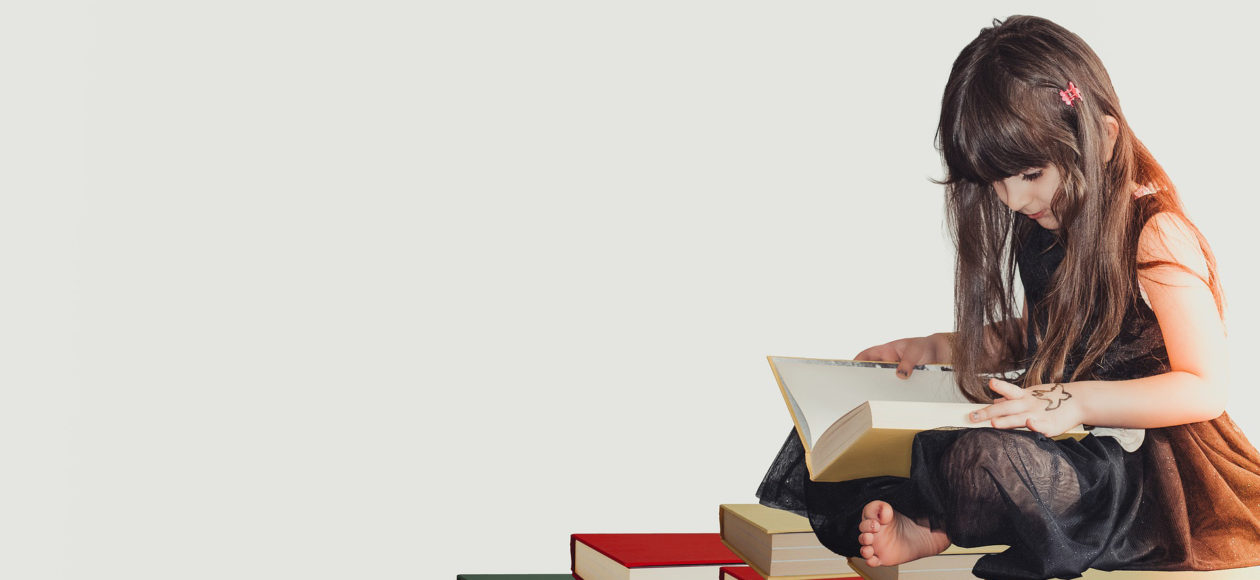こうした知見を持って語れることは
「大学とは何か」(吉見俊哉)岩波新書

現代における大学の危機とは
いかなる危機なのか。
教養の崩壊と学生の学力低下、
大学の可能性や学位に対する
驚くべき世間の無理解、
教職員の定員削減と
新自由主義的価値の浸透といった
現実に日々接していると、
今やこの国で…。
「大学って何ですか」。
本書を読み始めたきっかけは、
中学校の現場で
よく生徒から投げかけられる問いに、
説得力ある解答をつくる
手がかりを得るためでした。
読み始めて早々、
「しまった!」と思いました。
そう簡単に答えを提示してくれるような
易しい本ではありません。
【本書の章立て一覧】
序章 大学とは何か
Ⅰ章 都市の自由 大学の自由
1 中世都市とユニヴァーシティ
2 学芸諸学と自由な知識人
3 増殖と衰退―大学の第一の死
Ⅱ章 国民国家と大学の再生
1 印刷革命と「自由な学知」
2 「大学」の再発明
―フンボルトの革命
3 「大学院」を発明する
―英米圏での近代的大学概念
Ⅲ章 学知を移植する帝国
1 西洋を翻訳する大学
2 帝国大学というシステム
3 「大学」と「出版」のあいだ
Ⅳ章 戦後日本と大学改革
1 占領期改革の両義性
2 拡張する大学と学生叛乱
3 大綱化・重点化・法人化
終章 それでも、大学が必要だ
あとがき
主な参照文献一覧
※詳しくはこちらから(岩波書店HP)
本書は、様々な問題を抱え、
変革の時期を迎えている
(今に始まったことではないが)大学の、
本来あるべき姿と
未来に向けての在り方を探るために、
大学の歴史を俯瞰し、
その原点に戻って
考えようとするものです。
「序章 大学とは何か」では、
そうした問題提起と、
その解決のために展開する
論旨の概略が記されています。
「Ⅰ章 都市の自由 大学の自由」では、
中世ヨーロッパで始まった大学が、
隆盛と衰退を経て、いかにして
世界に広がっていったかについて、
その歴史が記されています。
なぜここまで
歴史を遡る必要があるのか?
著者の見解は明確です。
「大学の概念が空洞化したのは
現代が最初ではない」。そして
「大学はこれまで、
少なくとも二度の誕生と一度の死を
経ている」。
著者はその歴史を紹介する中から、
問いに対する解答の手がかりを
可視化していきます。
問いに対するⅠ章での鍵は
「キリスト教世界における
欧州都市間のネットワークが
中世の大学の本質」であると
いうことでしょうか。
「Ⅱ章 国民国家と大学の再生」では、
十六世紀以降の流れとして、
図書館や博物館等の文化施設の拡充や
印刷技術の進歩による
書籍の流通の拡大を取り上げ、
大学がそうした「メディア」としての
役割を担ってきたことを
著者は詳らかにしていきます。
この段階で、Ⅰ章で紹介された
大学の「中世モデル」は衰退し、
近代的モデルへと移行したことが
示されます。
問いに対するⅡ章での鍵は
「国民国家を基盤とした
近代的大学モデルの誕生と
印刷革命による
大学のメディア化」ということだと
考えられます。
「Ⅲ章 学知を移植する帝国」で、
舞台はようやく
維新後の日本へと移ります。
私たちの国がどのような理想像を描いて
大学を創り上げたかが
語られていきます。
西洋的大学移植から始まった
日本の大学機構は、
「帝国大学」の名が示すとおり、
「帝国(=天皇)」のための大学へと
姿を変えます。
そこで学ぶ「知」とは、
「天皇のまなざしの下で編成される
「帝国」の知」であると
著者は解き明かしています。
問いに対するⅢ章での鍵は
「西洋とは異なった形に変化した
日本の帝国大学モデル」なのでしょう。
「Ⅳ章 戦後日本と大学改革」では、
戦後における日本の大学改革が、
どのような意図を持って
行われていったのかが
述べられています。
戦後の学制改革は、
米国からの押しつけではなく、
ある日本人の勢力が
押し進めたものであること、
60年代末における学生運動の本質は、
大学の本来あるべき姿への
学生からの希求であること、などが
取り上げられています。
問いに対するⅣ章の鍵は
「戦後の日本の大学の抱えた
矛盾・混乱の原因は
大学の使命感の崩壊」と考えます。
そして
「終章 それでも、大学が必要だ」では、
Ⅰ~Ⅳ章で示されたことを
再構築しながら、
著者は持論を展開していきます。
「大学とは何か」という
壮大な主題に対し、
歴史の中からその問いに対する
鍵を見つけ出し、
それらを有機的に統合していくことで、
その解答を導き出そうとする
著者の試みは成功しています。
読み終えると、
緻密で壮大な建築物の内部を
観覧したような気分になります。
極めて高密度な内容であり、
岩波新書の中でも出色の完成度を誇る
一冊といえます。
強くお薦めしたい一冊です。
自分自身に戻って、ではここから
生徒にどう伝達するかと考えると、
頭を抱えざるを得ないのですが、
こうした知見を持って語れることは、
これまで以上に説得力ある
説明となるのではないかと
思っています。
※本書の続編的一冊が
すでに出版されています。
同じ岩波新書からの
「大学は何処へ 未来への設計」です。
こちらも読んでみたいと思います。
(2022.9.20)

【吉見俊哉の本】
【関連記事:学びに関わる本】
【岩波新書はいかがですか】
【今日のさらにお薦め3作品】