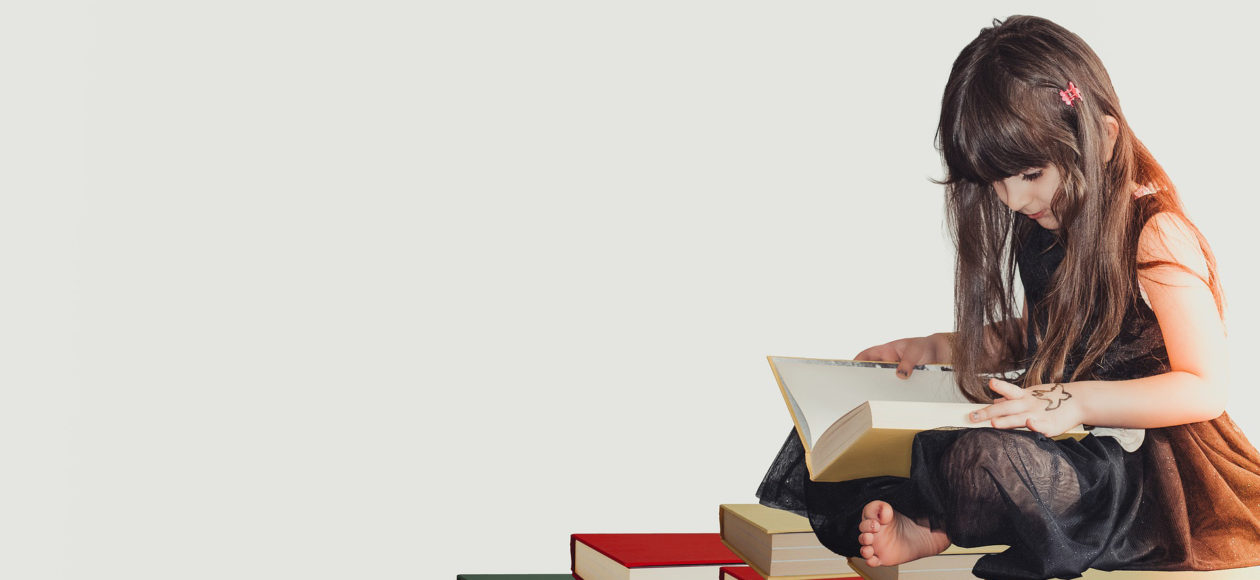もう一度君の身のまわりを見てごらん
「武蔵野」(国木田独歩)新潮文庫

武蔵野の美は落葉樹の林にある。
ツルゲーネフ/二葉亭四迷訳の
「あひびき」から
私はそれを教えられた。
武蔵野のもう一つの魅力は
野にある。
これもまた「あひびき」の
自然描写に通じるものがある…。
あらすじを書くような作品では
ないのかも知れません。
本作品は作者・国木田独歩が
明治29年の秋に
東京郊外に広がる「武蔵野」を半年間、
毎日のように散策を重ね、
そのときの日記をもとに書き上げた
自然を賛美した短篇なのです。
言うまでもなく今現在の武蔵野は、
明治29年当時とは違い、
その自然の風景の多くを失っています。
国木田独歩が賞賛した自然の美を
追体験することなど不可能でしょう。
「今となっては…」という感想が
聞かれるのも当然かも知れません。
では、現代の私たちにとって
本作品を読む意味は何か?
私が注目している一節は
以下の部分です。
自分はある友と市中の寓居を出でて
三崎町の停車場から境まで乗り、
そこで下りて北へ真直に四五丁ゆくと
桜橋という小さな橋がある、
それを渡ると一軒の掛茶屋がある、
この茶屋の婆さんが自分に向かって、
「今時分、何にしに来ただア」と
問うたことがあった。
自分は友と顔見あわせて笑って、
「散歩に来たのよ、
ただ遊びに来たのだ」と答えると、
婆さんも笑って、
それもばかにしたような笑いかたで、
「桜は春咲くこと
知らねえだね」といった。
このお婆さんにとっての
美しい景色とは、春の桜以外に
考えられなかったのです。
小金井は桜の名所、
それで夏の盛りにその堤を
のこのこ歩くも
よそ目には愚かにみえるだろう、
しかしそれはいまだ今の武蔵野の
夏の日の光を知らぬ人の話である。
咲き誇り乱れ散る桜を
美しいと感じるものの、
夏の林の美しさには気付かない。
それが独歩の時代の
一般人の感覚だったのですが、
それは現代人にも通じると思うのです。
いや現代人であればなおさらでしょう。
もし独歩が現代に生きていたら、
失われた自然の多さに嘆息しながらも、
残された自然の中に
私たちの気付かない美しさを
幾つも指摘していたのではないかと
思うのです。
現代に生きる私たちが
本作品から学ぶべきは、
独歩のこの
「自然の美に気付く眼と心」なのでは
ないでしょうか。
もう一度君の身のまわりを見てごらん。
「武蔵野」を再読するたびに、
独歩の優しいささやきが
聞こえてくるような気がします。
(2018.10.5)

【青空文庫】
「武蔵野」(国木田独歩)