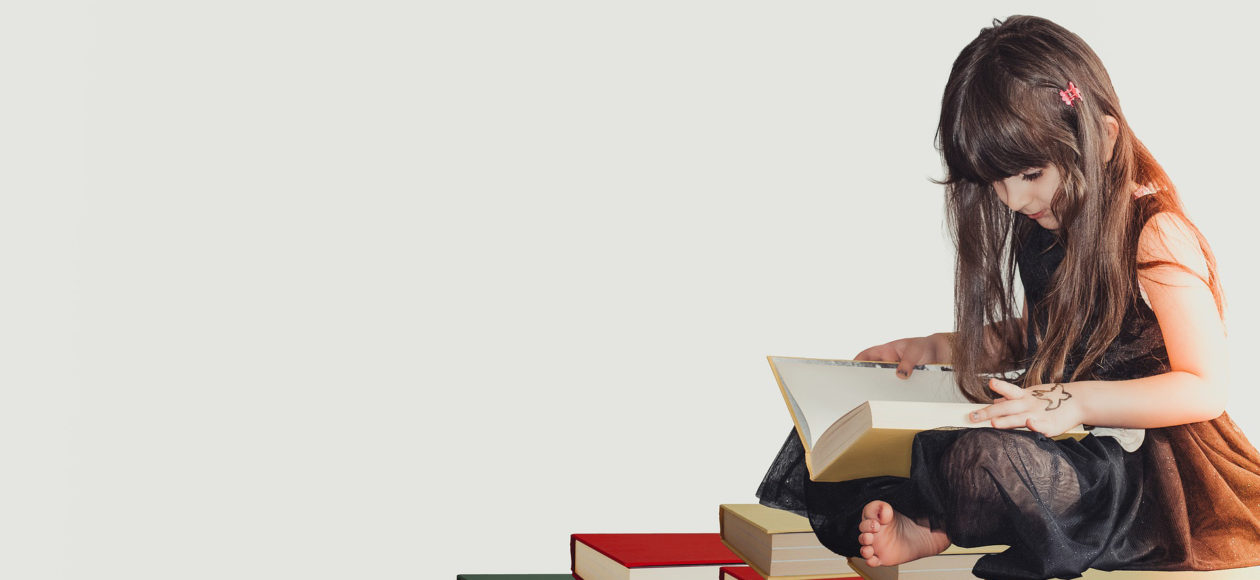渾身すぎてかえってぎくしゃくしている本作品
「虞美人草」(夏目漱石)新潮文庫

本書のカバー裏を見ると、
「東大教師を辞め
職業作家になる道を選んだ
漱石渾身の一作」とあります。
しかし、各種の書評を見る限り、
渾身すぎてかえって
ぎくしゃくした部分の多い作品と
見られているようです。
渾身すぎる部分①
一人称なのか三人称なのかわからない
登場人物を甲野さん、宗近君と
表しているため、
「私」が登場する一人称私小説かと
思ってしまいます。
しかし、最期まで「私」の登場しない
三人称小説なのです。
渾身すぎる部分②
言葉は難解、描出は詳細
知識人階級にしか伝わらないような
難しい言い回しを多用しているため、
すこぶる読みにくいのです。
それでいて人物の心情描写は、
現代の漫画のように事細かく
すべてを伝えようとしています。
渾身すぎる部分③
人物配置は複雑、筋書きは単純
本作品は、
実は最期に藤尾が亡くなります。
まるで藤尾がすべて悪く、
天罰を受けたかのような
明快な筋書きです。
人物配置を複雑にする一方で、
筋書きは単純。
巻末の解説によると、
旧来の勧善懲悪形に
なっているのだそうですが。
本作品は、このような
どっちつかずの要素を含んでいる、
とらえ方に難渋する作品なのです。
それはあたかも
主人公・小野の性格に重なります。
①については、
職業作家となった漱石の、
新しい小説の可能性の
模索ではないかと私は考えます。
専門家はどのような判断を
なされているのかわかりませんが。
②③については、
知識人に侮られないような
表現や構成にしながらも、
自分の伝えたいことを
100%伝えることを目指した
折衷的スタイルと
考えることができます。
こうした諸々のことを考え合わせるに、
本作品はまさに、
「東大教師を辞め
職業作家になる道を選んだ漱石」の、
試行錯誤の末に生み出された、
まさに「渾身の一作」であり、
後に生まれる傑作群に至る
出発点なのだと思うのです。
漱石の時代からすでに100年が過ぎ、
さまざまな分析が発表された後で
このような拙い私見を述べることは
甚だ恥ずかしい限りです。
しかし、私にはこの作品が
とてもいとおしく
感じられてならないのです。
学生時代にあれだけ読んだ漱石の、
私がこれまで避けてきた本作品。
もっと早く出会うべきでした。
反省。
※本記事は2016年3月に
他のブログに投稿したものを
リライトしたものです。
(2019.4.4)

【青空文庫】
「虞美人草」(夏目漱石)