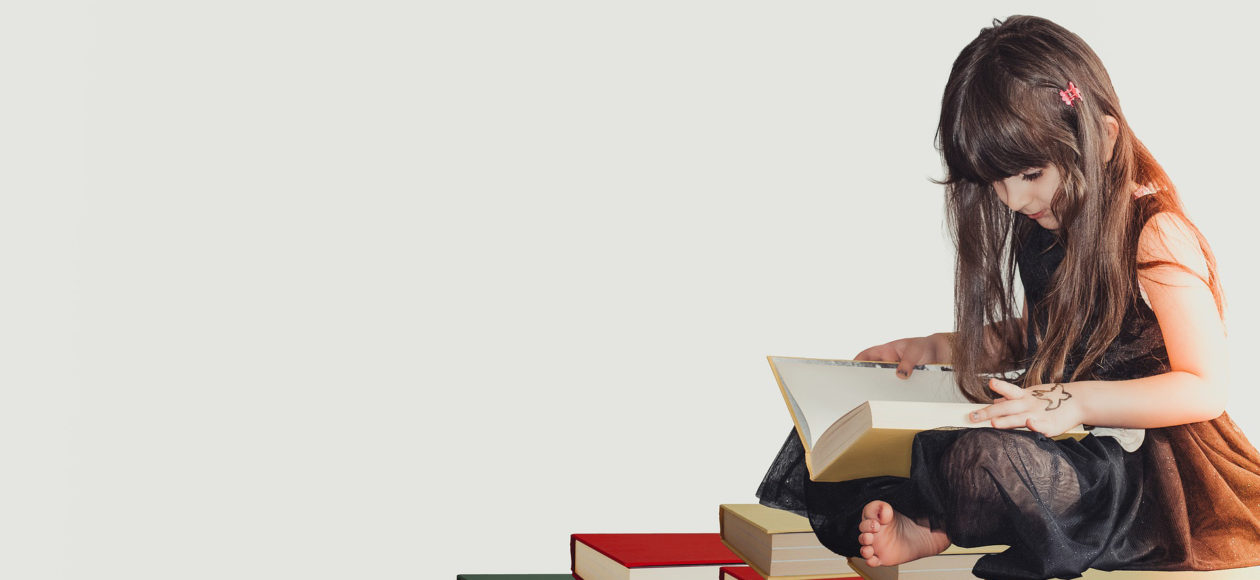舞台と時代の設定から見えてくる作者の警告
「蠅の王」
(ゴールディング/平井正穂訳)
新潮文庫

前回は本書「蠅の王」について、
登場人物の役割から
作品を考察してみました。
今日は舞台背景について考えてみます。
着目したいのは
少年たちが不時着した
島の環境についてです。
「無人島に生きる十六人」
(須川邦彦)では、
飲み水(真水)を得るために
何度も井戸を掘り、
相当な難儀をしています。
でも、この島には
真水がしっかりと湧き出ています。
「ロビンソン漂流記」をはじめとする
多くの漂流記では、
水に次いで食糧の確保に
苦労することになります。
でも、この島には
多くの果実が枝もたわわに実り、
食糧には困らないのです。
「十五少年漂流記」では
冬を越えるのに難渋していました。
でも、この島の気候は穏やかであり、
昼夜の気温の変動も
スコールのような大雨の心配も
なさそうです
(季節の変化を気にするほど
長期間の滞在ではなかったから
かも知れませんが)。
命をつなぐ、というだけなら
無人島としては極めて良好な環境です。
しかし、食うには困らないはずの島で、
豚の狩猟を始めてから
少年たちの関係は軋み始めます。
より美味いものを食いたいという
この「狩猟」こそ、
近代化もしくは資本主義を
表しているのではないかと思うのです。
必要以上のものを
得ようとする人間の欲望。
それを抑えきれなかった
ジャックの一味は
暴走をはじめることになったのです。
もう一つ注目したいのは時代背景です。
本作品は近未来の
戦時中ということになっています。
ラーフの窮地を救った
海軍士官はこう言います。
「きみたちみんな
イギリスの少年だろう?
もっと立派に
やれそうなもんじゃなかったのかね」。
しかし彼は同時に、
「沖合遥かに停泊している
端正な巡洋艦の姿に、
じっと眼をそそいでいた」。
少年たちが狭い島の中で
無益な殺し合いをしている
その外側の世界では、
大人たちが第3次か4次か
わかりませんが、大規模な戦争を
繰り返していということが
うかがえます。
「立派に」できなかったのは
少年たちだけではなかったのです。
足るを知ることに気付かなければ、
そして物質的豊かさを求め続ける
人間の本質が変わらなければ、
子どもたちにも大人社会にも
明るい未来はない。
舞台と時代の設定からは、
作者のそうした警告が
見えてきそうです。
いずれにしても
それまでの漂流物語とは一線を画す、
当時としてはエポックメイキング的な
作品だったことは間違いありません。
(2019.6.21)