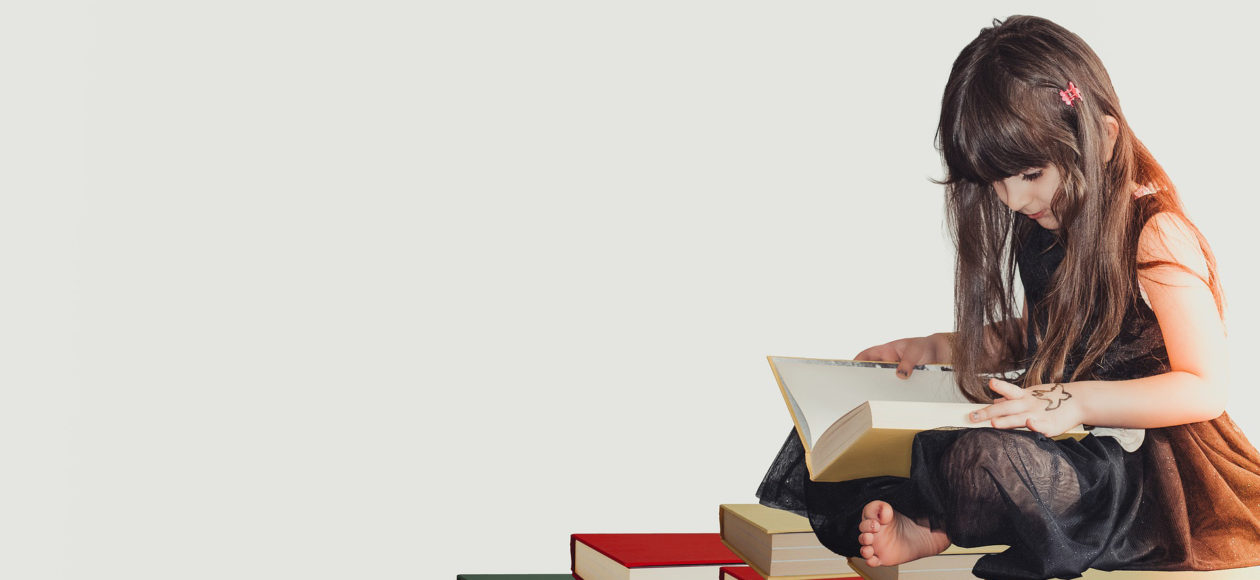貧乏に負けずに生きている二人の姿が眩しい
「馬乃文章」(林芙美子)
(「百年文庫003 畳」)ポプラ社

「馬乃文章」(林芙美子)
(「風琴と魚の町・清貧の書」)
新潮文庫

三文文士の「僕」の女房は、
大工や左官工のように
元気がいい。
めそめそしないので助かるが、
金がなくなると
「馬を食いたい」と云って困る。
貧乏続きでとうとう
家を追い出されるその日、
朝から女房の姿が見えない…。
林芙美子得意の貧乏生活物語です。
ただし本作品は男性一人称。
甲斐性のない文士「僕」と、
活力に溢れた妻の
日常を描いたものです。
この二人の人物像を
味わう作品といえるでしょう。
「僕」は脳天気で屈託のない人間。
筆名を20数回変えてみるものの
一向に売れない作家。
したがって貧乏を極めます。
家賃滞納で立ち退きを迫られ、
金を作るため通信社に
原稿を売りに行くのですが、
その金で仲間と
飲んでしまうという有様です。
まあ、ダメ男と言ってもいいでしょう。
その妻は生命力のある女性です。
貧乏作家の夫と
喧嘩もせずにやっているだけでも
立派なものです。
さらに、家を明け渡す日の朝から
姿を消していたのは、
よいとまけ(日雇い労働)に
行っていたからなのです。
何とも健気な女房です。
それにしても本作品、
「馬肉」が実に効果的に
小道具としての役割を果たしています。
「帰りに馬を買ってくるから」と
家族を安心させておいて、
それが裏切られる。
「馬肉」を食えるか食えないかが
幸不幸の分かれ目のように
扱われています。
立ち退きの際には
唯一の家財道具「鍋釜」を
屑屋に売り払います。
この鍋釜が
馬肉を煮炊きしていたのですから、
これですべて失ったことを
感じさせるのに役立っています。
よいとまけに出ていたた
妻が買ってきた馬肉を、
家族でつつき合います。
「馬肉」が
家族の団欒の証となっています。
豚肉が十分に安くなった現代では、
馬肉というと
馬刺ししか連想できないのですが、
本作品に登場する馬肉は
おそらくバラ肉やすじ肉などの
部位と推察されます。
肉を食いたくても
豚や牛にはなかなか手が出せない。
だからわざわざ遠くへ
探しに行ってまで馬肉を買う。
貧乏であっても美味いものを
食いたいという前向きな気持ちが
そこに現れています。
友人宅に間借りしながら、
「僕」は売れない作品を描き続け、
妻はよいとまけに通い続ける。
現代に置き換えると
悲惨な生活なのですが、
暗さは微塵も感じられません。
「まだ、何も書いていないが、
軈て、何かいいものが
書けるだろう。」
貧乏に負けずに
たくましく生きている二人の姿が
眩しいほどです。
(2019.9.8)