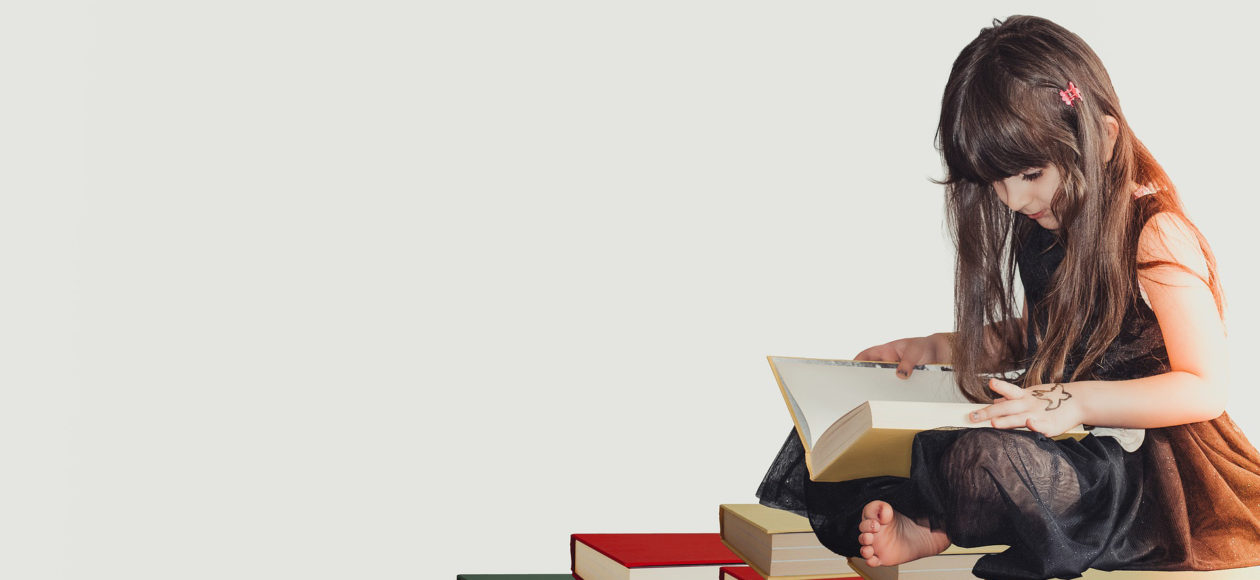子どもに夢を託すしかなかったちか女の半生
「胡桃林」(井上靖)
(「姨捨」)新潮文庫

「私」は十二、三歳の頃に
磯川ちか女と知り合う。
ちか女は若くして
未亡人となったものの、
投機的資質と大胆な性格から
資産を増やし、
三人の子どもの
英才教育を行っていた。
彼女がもっとも情熱を傾けたのは
次男・正章であったが…。
彼女の夫は将来を嘱望された
有能な工学博士でした。
夫の出世を夢見ていた彼女は、
それを子どもに託すのです。
しかし、長男・義春は学才に秀でず、
長女・かつらは優秀であるも
女であるため、
その愛情はすべて、
頭脳明晰であり
将来の大成を期待できる
次男・正章だけに注がれたのです。
その正章は、親からの束縛を嫌い、
自らの人生を歩みます。
すると彼女は正章の子
(彼女にとっては孫)の仙太郎に
すべてを託そうとします。
ところがその仙太郎は自ら命を絶ち、
彼女の夢は潰えるのです。
「教育ママ」という言葉を
最近聞かなくなりましたが、
私の子どもの頃は
よく耳にした記憶があります。
もしかしたら本作品のちか女は、
「教育ママ」の
先駆け的存在なのかも知れません。
子どもの人生に
親の価値観を押しつけるのは
失敗のもとということなのでしょう。
愛情を受けることのなかった
義春・かつらも気の毒ですが、
正章・仙太郎も
哀れに思えてなりません。
ちか女自身が
学問優秀の才女なのです。
加えて投機の才もあり、
勝負所の決断力も抜群です。
さらには美貌にも恵まれているのです
(中年以降は肥満体型となるのですが)。
現代であれば一流の研究者、
もしくは辣腕の投資家として
名を為すことができたはずです。
本作品発表は1954年。
戦後間もない頃です。
いかに能力があろうとも、
女性が活躍できる
時代ではなかったのです。
自分の能力を
社会で試せないのであれば、
夫や子どもに
夢を託すしかなくなるのでしょう。
性別に関わりなく、
自分の力を生かすことができる社会。
政権が「一億総活躍社会」という
政策を掲げている現代ですが、
女性はどこまで
活躍できているのでしょうか。
「教育ママ」なる言葉が
存在感を失ってきたことは、
そうした動きが少しずつでも
始まっていることと
いえるのかも知れません。
架空の人物を描いた
短篇作品でありながら、
まるで歴史小説を読んだような
読後感がありました。
やはり井上靖は
現代を扱った作品であっても
味わい深さが格別です。
本当の大人が読む
作品といえるでしょう。
(2019.10.26)