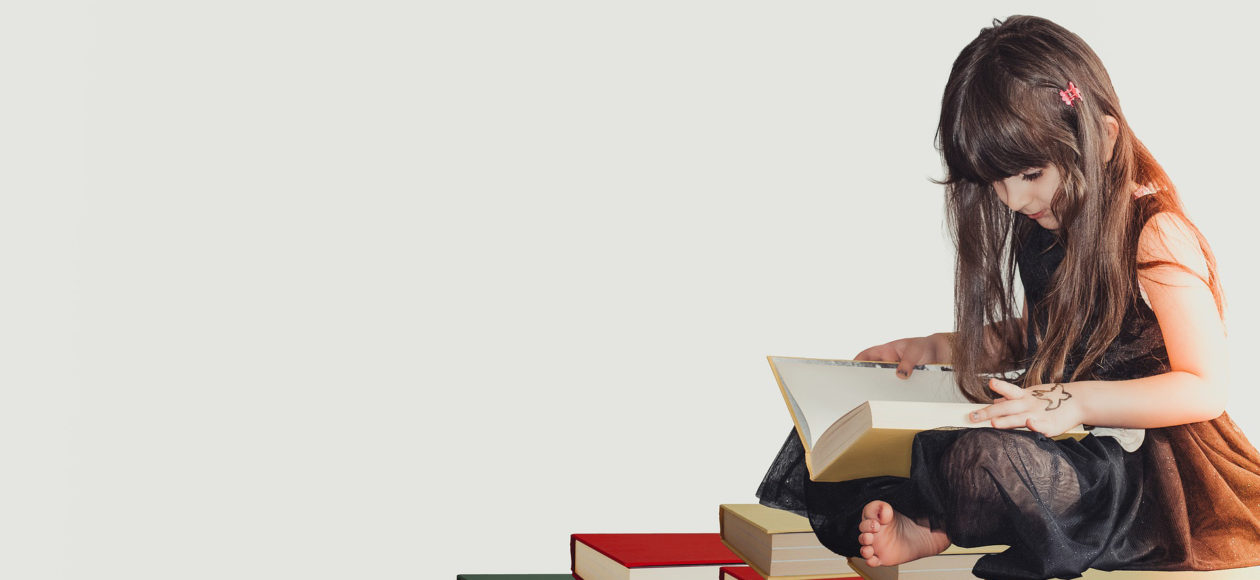作者魯迅の厳しい生き方が反映されています
「小さな出来事」(魯迅/竹内好訳)
(「百年文庫008 罪」)ポプラ社

先を急いでいた
「私」の乗った人力車が、
飛びだしてきた老婆と接触した。
老婆はゆっくりと倒れただけで
心配はないようだ。
「何ともないよ」という
私の言葉に耳を貸さず、
車夫は老婆を助け起こすと、
ためらわずに派出所へ向かった…。
短いながらも、
読み手にいろいろなことを考えさせる
魯迅の傑作です。
「私」はこの出来事を
はじめは「小さ」く捉えていたのです。
「その老婆が
けがをしたとは思えなかったし、
ほかに誰も見ていないのだから」。
そして老婆にこそ非があるとも
考えはじめています。
「狂言にきまっている。
じつに憎いやつだ。」
さらには車夫にまで不満を覚えます。
「車夫も車夫だ。
おせっかいの度がすぎる。」
しかし車夫の誠実な姿を見たとたん、
「私」の感覚が変化します。
「車夫のうしろ姿が、
急に大きくなった。
そしてついに、
防寒服に隠されている私の「卑小」を
しばり出さんばかりになった。」
車夫を拘束したことを
告げに来た巡査に対して「私」は、
ひとつかみの銅貨を渡します。
その自らの行為もまた
「私」に迫ってきます。
「このひとつかみの銅貨は
何の意味か。
かれへのほうび?
私が車夫を裁ける?」
とっさに出た行為さえ、
自身の「卑小」さを
さらに明確にしたに過ぎなかったことに
気付いているのです。
この作品が
読み手の心に突き刺さってくるのは、
「私」の「驕り高ぶった気持ち」と
「自分の矮小さ」、そして
それらに「自ら気付く心」の三つが、
鮮明に描かれているからなのです。
誰しもが持ち合わせている
「利己的な考え方」と、
誰しもが認めたくない
「己の小ささ」と、
誰しもが持ち合わせているわけではない
「自分自身を客観的に見つめる視線」
(いわゆるメタ認知)。
これらが実によく
描出されているのです。
作品の冒頭に書かれてあるように、
「私」が北京に来てからの歳月は、
「日ましに私を人間不信に
陥らせただけ」だったのです。
おそらくは、多くの人間の、
私利私欲のために生きている姿を
目の当たりにしてきたからでしょう。
それなのに自分もまた
「利己的な考え方」に
支配されていたことに気付いた「私」。
作者・魯迅自身の
厳しい生き方が反映されています。
中学生の頃に初読して以来、
読み返すたびに
「お前はどうなのだ?」と
詰問されているような感覚を覚えます。
こうした生き方を、50を過ぎた現在も、
できている自信が全くありません。
※この竹内好訳が
最も有名だと思いますが、
光文社文庫刊の藤井省三訳は
もっとこなれていて
やわらかな印象を受けます。
訳者によってこうも雰囲気が
変わるものかと驚きます。
(2019.12.15)