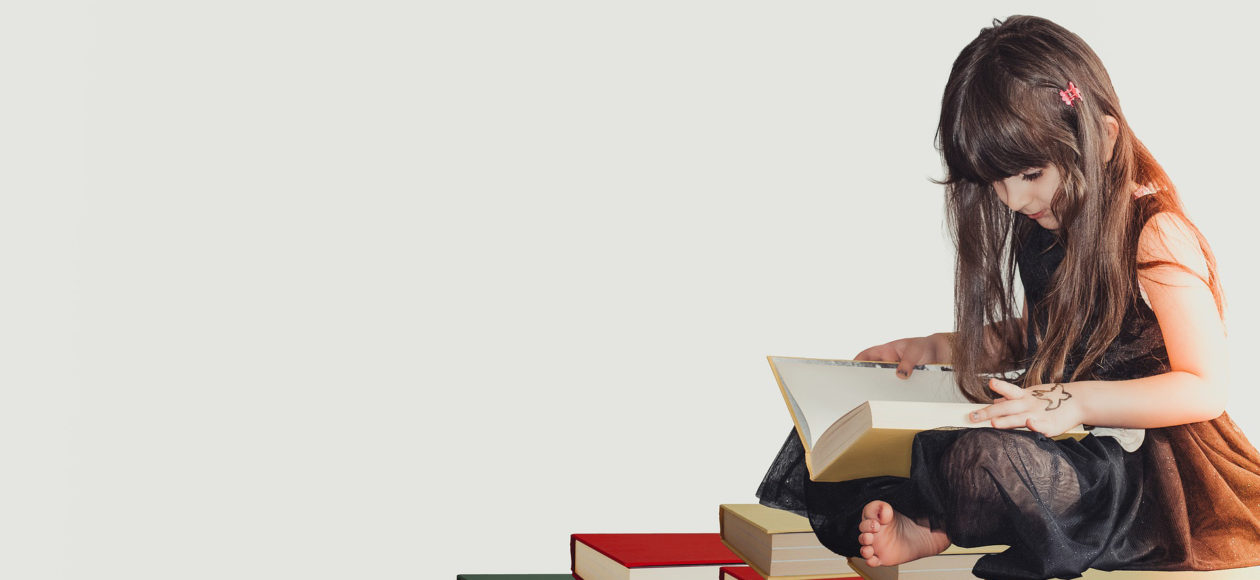多くは画家の口から語られる芸術論です
「草枕」(夏目漱石)新潮文庫

山中の温泉宿に投宿した
画家の「余」は、その宿の
「若い奥様」・那美と知り合う。
出戻りの彼女は、「余」にとって
「今まで見た女のうちで
最も美しい所作をする
女」であった。
「余」はその那美から
自分の画を描いて欲しいと
頼まれる…。
画家はどうしたか?
彼は、彼女には
「足りないところがある」ことを感じ、
描こうとしませんでした。
足りないものとは何か?
それは終末で
明らかにされるのですが…、
別れた夫と発車する
汽車の窓ごしに見つめあった
那美の顔に浮かんだ「憐れ」なのです。
「余」は「それだ、それだ、
それが出れば画になりますよ」。
本作品に画家が
絵を描いている場面は登場しません。
画家はこの地に来て以来、
絵を描いていないのです。
描かなくとも、
「余が胸中の画面は
この咄嗟の際に成就したのである」。
画家の描かれざる絵と同じように、
本作品もまた「書かれざる小説」と
言うべきなのでしょう。
なぜなら筋書きらしいものが
ほとんど存在しないからです。
作中で「余」は、「非人情」なる言葉を
何度か口にしています。
人情、つまり人間の情から
生み出される筋書きを排し、
「美」について語るという
手法をとっているのです。
「いくら惚れてもあなたと
夫婦になる必要はないんです。
惚れて夫婦になる
必要があるうちは、
小説を初から仕舞迄
読む必要があるんです」
「すると不人情な
惚れ方をするのが画工なんですね」
「不人情ぢやありません。
非人情な惚れ方をするんです。
小説も非人情で読むから、
筋なんかどうでもいゝんです。
かうして、御籤を引くように、
ぱつと開けて、開いた所を、
漫然と読んでるのが面白いんです」
多くは画家の口から語られる
芸術論です。
絵画のことを論じているのですが、
それを文学に置き換えると、
それはすなわち漱石自身の
文学観・芸術観になるはずです。
不勉強な私には
よく分からないのですが。
分からないなりに
読み応えのある作品です。
なぜなら本作品には、
漱石の後の作品に見られるような、
重苦しい「文明と個人の葛藤」の
要素の存在が極めて薄いからです。
西欧化の波間に漂う
日本人が綴られているものの、
それはまだ漱石の中では
文学の主題としては
熟成していなかったものと
考えられます。
これで三度読み通しましたが、
やはり難しい。
死ぬまでの間にもう何度か読んで、
この作品世界に
もっと深く入りこんでいきたいと
考える今日この頃です。
(2018.10.1)

【青空文庫】
「草枕」(夏目漱石)