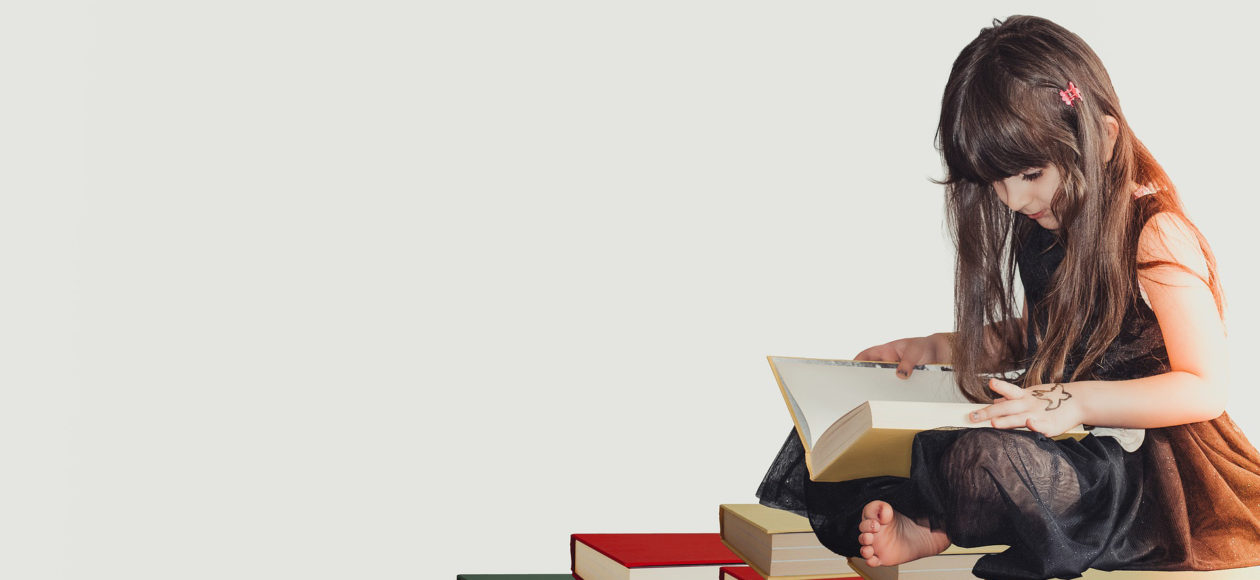圧倒的なセリフの力で強引に読み手をねじ伏せる
「卵の緒」(瀬尾まいこ)新潮文庫

僕は捨て子だ。
その証拠に母さんは僕に
へその緒を見せてくれない。
そして母さんは四月から
いつも同じ話を繰り返す。
朝井さんの話だ。
何でも母さんの職場に
転勤してきた男のひとらしいけど、
ものすごくかっこいいらしい…。
年をとればとるほど、
涙腺がもろくなってきました。
普段はテレビ番組など見ないで
書斎にこもり、
本を読んだりCDを聞いたり…。
でもたまにTVドラマなんぞを見ると
涙が出て止まらなくなります。
だからこそ、TVドラマを
見ないようにしているのですが。
そんな私は本作品を読むと、
いつも涙があふれます。
セリフが泣かせるのです。
筋書きそのものは、
冷静に考えると、
「そんなのあるわけないだろう」と
思うのです。
でも、
セリフの力が圧倒的にすばらしい。
母子家庭の郁生は、
小学校の先生から
「へその緒」の話を聞き、
それを母に尋ねます。
「ねえ、へその緒っていうの出して」
「へその緒?」
「ほら、母さんのおなかと
子どもを繋げているやつ」
「ほう。日本には
そんな便利な代物があるのか」
軽妙なセリフが冒頭から並びますが、
クライマックスでは、
感動の雨あられです。
「長い話になったけど、
結論は母さんと郁生は
血が繋がっていないと言うこと。
そして、母さんは誰より
あなたを好きだってこと」
「想像して、
たった十八の女の子が
一目見た他人の子どもが欲しくて
大学辞めて、
死ぬとわかっている男の人と
結婚するのよ。
そういう無謀なことができるのは
尋常じゃなく愛しているからよ。
あなたをね。
これからもこの気持ちは
変わらないわ。」
「そんなのあるわけないだろう」
そう思っていても泣けてきます。
設定には無理があるものの、
本作品は圧倒的なセリフの力で
強引に読み手をねじ伏せる
不思議な力を持っています。
あとがきを読むと、
著者もまた
父親を持たない家庭で育ったとのこと。
だからなのでしょう、
著者の求める家族のあり方が
現れているのだと思います。
家族って何だろう、
血の繋がりって何だろう、
そう考えさせられる作品です。
多分、大人向けに書かれた
癒やしの小説だと思うのですが…、
中学校1年生にぜひ薦めたい作品です。
(2018.12.06)